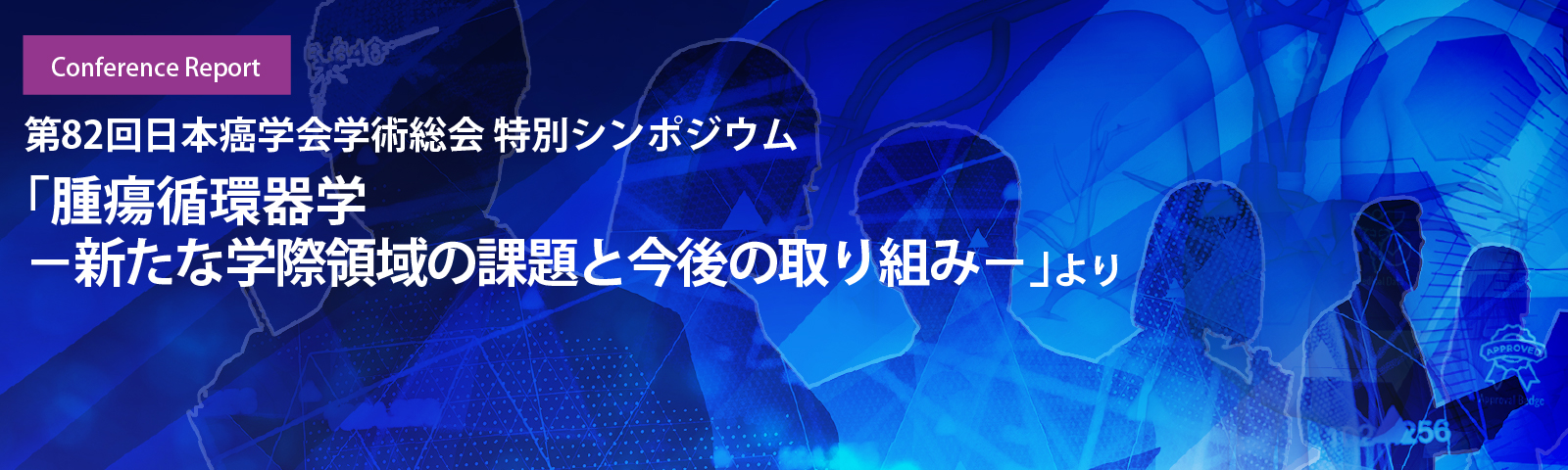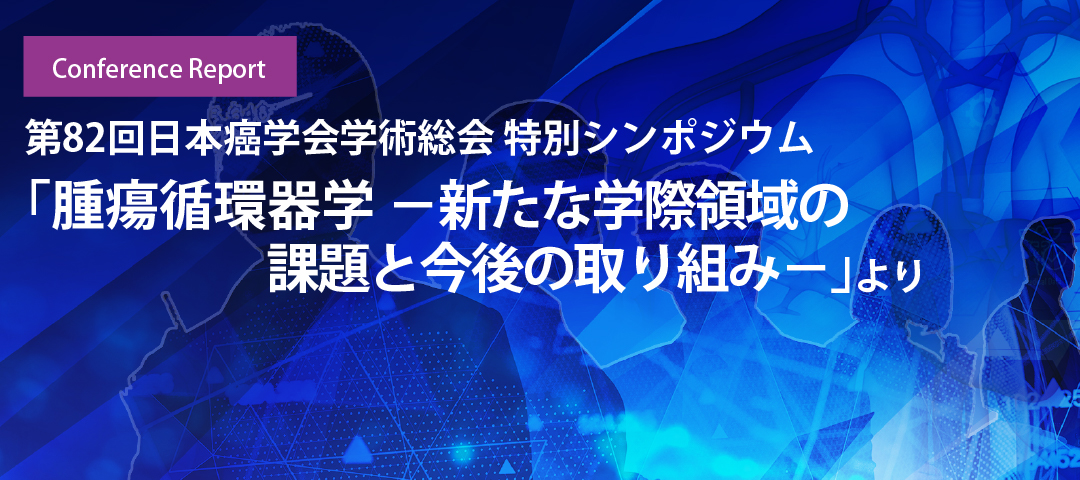第82回日本癌学会学術総会が2023年9月21日から23日の3日間にわたり、パシフィコ横浜で開催された。最終日の23日には日本腫瘍循環器学会との2学会合同で特別シンポジウム「腫瘍循環器学 -新たな学際領域の課題と今後の取り組み-」があり、腫瘍循環器学をめぐる最新トピックスが紹介された。

- 写真1国際医療福祉大学副学長で日本腫瘍循環器学会前理事長の小室一成氏
トップバッターとして登壇した国際医療福祉大学副学長で日本腫瘍循環器学会理事長(当時)の小室一成氏(写真1)は、「腫瘍と循環器はお互い遠い離れた領域であったが、55歳以上の3人に1人が心不全に2人に1人ががんを罹患する時代となり、両方の疾患を合併している患者の数も増えている。さらにがん治療薬の中には血管を障害するものが多く、血栓を誘発するケースも多く、腫瘍循環器への積極的な取り組みが望まれている」と腫瘍循環器の意義を語りかけた。
がん治療による心筋障害と遺伝子変異の関係に注目
さらに同氏は「今年は日本臨床腫瘍学会・日本腫瘍循環器学会が、日本癌治療学会、日本循環器学会、日本心エコー図学会の協力を得て念願だったOnco-cardiologyガイドラインを刊行した画期的な年となったが、その一方でこの分野でエビデンスが少ないことが大きな課題として再認識されるに至った」と述べた。
エビデンス構築のためには臨床研究が必要だが、今年度(令和5年度)は厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)に「がん患者に発症する心血管疾患・脳卒中の早期発見・早期介入に関する研究」(23EA1036)が採択された。
小室氏は注目する研究のトレンドとして、がん治療に伴う心筋障害にかかわる遺伝子変異が注目されているとし、腫瘍循環器に対する分子標的治療が発展する可能性を示唆した。

- 写真2東北大学大学院医学研究科臨床腫瘍学教授で日本臨床腫瘍学会理事長の石岡千加史氏
腫瘍循環器の今後の課題として同氏は、①腫瘍循環器の認識の普及と教育の拡充、②腫瘍循環器に対応する医療体制の確立、③ガイドラインの啓発・普及、④登録、介入などの臨床研究の促進、⑤基礎研究の促進と病理の解明、⑥産官学連携を通しての戦略的イニシアチブの促進、の6つを指摘した。
続いて登壇した東北大学大学院医学研究科・臨床腫瘍学教授で日本臨床腫瘍学会理事長の石岡千加史氏(写真2)は、第4期がん対策推進基本計画の中に「腫瘍循環器学や腫瘍腎臓病学等のがん関連学際領域に対応できる人材や医療ビッグデータの解析専門家、個別化医療・創薬研究を担う人材」の育成が重要な課題と明記されたことを踏まえ、腫瘍循環器の注目が高まっていることを強調。加えて「現在は主に循環器疾患を併発するがん患者への対応にフォーカスされているが、将来は心不全など循環器疾患の患者にがんが見出されるケースが増えてくることも予想され、腫瘍医と循環器医との連携がますます重要なものになる」と展望した。
ICI心筋症への対策の確立が課題

- 写真3国立がん研究センター東病院循環器科長で筑波大学グローバル教育院准教授の田尻和子氏
多くの未解明の課題を抱える腫瘍循環器のなかでも早急に解決されるべき問題が免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の使用で誘発される重篤な心筋症の予防と対策だ。国立がん研究センター東病院循環器科長で筑波大学グローバル教育院准教授の田尻和子氏(写真3)は、「ICIに合併する心筋症の発症は稀だが、一度発症すれば致死率が高い劇症型心筋症である。ステロイドによる免疫抑制療法には抵抗性となることがしばしばあり、その後に取るべき2次的な免疫抑制療法が確立していない」と課題を指摘した。
田尻氏が経験した食道がんの症例では、最終的にECMO(体外式膜型人工肺)を必要とするほど重症化したが、重症化直前まで自覚症状に乏しかったという。「LVEF(左室駆出率)やBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)よりも心電図や心筋トロポニンの計測が信頼できるが、そこには個人差が大きいことも留意する必要がある」と指摘した。
積極的な治療法としては、関節リウマチの治療薬でT細胞活性化を抑制するアバタセプトやJAK1/2阻害薬が有望だ。JAK1/2阻害薬については無作為化臨床試験(RCT)が走っている。ただし、田尻氏は、これら強力な免疫抑制剤が、ICIがもつ抗腫瘍効果そのものを減弱させる可能性も否定できないとして、今後の展開を注目する姿勢を示した。
アップデートしないガイドラインは死ぬ
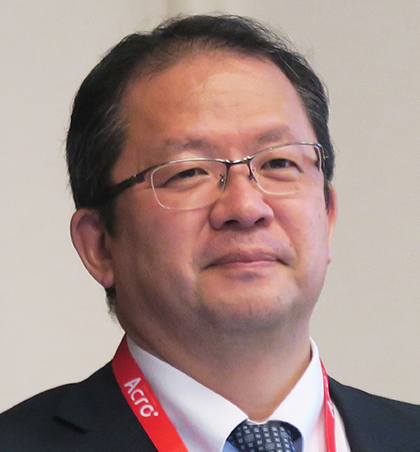
- 写真4大阪国際がんセンター成人病ドック科主任部長の向井幹夫氏
大阪国際がんセンター成人病ドック科主任部長の向井幹夫氏(写真4)はがんと静脈血栓塞栓症(VTE)の問題と抗凝固剤開発の最前線を解説した。「がん関連血栓症(CAT)は外来化学療法中のがん患者における死因の9.2%を占め、その約4割がVTEとされる」という。
海外では、がん関連VTEに対する標準治療は低分子ヘパリン(LMWH)だが、日本では承認されていない。製薬会社にも効能拡大する動きがないことから日本腫瘍循環器学会が薬事承認を求めて公知申請しており、現在厚生労働省で審査中だ。向井氏は「日本でもLMWHは一刻も早く承認されるべきだが、その後で導入され、日本の抗凝固療法の事実上の標準治療となっているDOAC(直接経口Xa阻害薬)もLMWHとの非劣性を証明する臨床研究が出ており、DOACの活用を考慮すべき」との考えを示した。
また現在、新規の抗凝固剤の臨床試験が進んでおり、これらが臨床現場に導入される2024年以降、血栓・塞栓治療を変革する可能性があると語った。
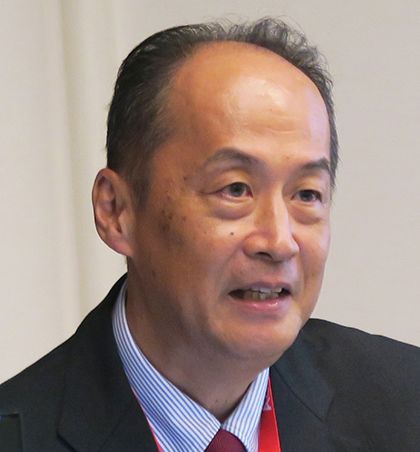
- 写真5順天堂大学大学院医学研究科臨床薬理学教授の佐瀬一洋氏
「国内外の腫瘍循環器学診療ガイドラインに示されたエビデンス・ギャップ」をテーマに口演したのは順天堂大学大学院医学研究科臨床薬理学教授の佐瀬一洋氏(写真5)だ。再三指摘されているように、若い学問である腫瘍循環器にはエビデンスが不足している。診療ガイドラインは通常、臨床研究の質を吟味し、エビデンスのレベルを評価したうえで作成されるが、「Onco-cardiologyガイドライン」ではエビデンスが少なく、ほかの臨床ガイドラインに比べ、ページ数も少なかった。
佐瀬氏はエビデンスが少ない段階でもガイドラインを作成する意味があると強調した。「不完全ながらもガイドラインを作っておけば今後の臨床研究の指針になる。大切なのは臨床現場で実践しつつ、問題解決に向け臨床研究を積み重ねてアップデートしていくこと。現在、この分野ではガイドラインが乱立しているが、アップデートされないガイドラインは死ぬ」と訴えた。
ヒトiPS細胞由来心筋を利用した化合物の評価

- 写真6国立医薬品食品衛生研究所・安全性生物試験研究センター薬理部長の諫田泰成氏
潜在的に心毒性や血管障害をもつ薬剤を使用したがん治療を、有効性を損なわずに安全性をいかに確保すべきかが腫瘍循環器の大命題だが、そもそも循環器への負荷をかけないがん治療薬が開発できないものか。その問いかけに応える可能性を秘めた研究成果を報告したのが最後に登壇した国立医薬品食品衛生研究所・安全性生物試験研究センター薬理部長の諫田泰成氏(写真6)だ。
諫田氏はヒトiPS細胞から誘導した心筋細胞(iPSC-CM)を使った化合物の評価系の構築と標準化を目指している。心毒性に関する試験は従来から動物実験で実施されてきたが、正確さに欠けるところがあった。「iPSC-CMを使ってヒト細胞を試験すれば、より正確な安全性を推測できるのではないかと検討を進めている」と語る諫田氏はJapan iPS Cardiac Safety Assessment(JiCSA)を主導して、新規試験法の開発と検証、国際標準化に進んでいる。これまで医薬品による心電図のQT延長症候群や致死性不整脈の発生予測に関して大規模な多施設検証研究を進めている。
iPSC-CMを利用した評価は不整脈や心不全のリスクの評価には適しているが、ICIの心筋炎や血栓・塞栓のリスク評価には利用することができない。しかし、前臨床かそれ以前の段階で、開発中の化合物のリスクを評価する製薬会社も増えていると、諫田氏は紹介した。